My Leica Story
ー 高木誠 ー
後編

ライカストア松坂屋名古屋店では、上高地の山河をフィールドとして長年に渡り撮影し続けている写真家、高木誠さんの写真展「生きている大地」を開催中(期間は2025年11月6日まで)。
大いなる自然を畏れ敬うとともに、その恵みに感謝する『日本人の自然観』を可視化した数々の作品を撮影したカメラはライカとのこと。そこでPart1に続いてライカのインプレッションと撮影のエピソード、ライカに寄せる思いを高木さんにお聞きしました。
text: ガンダーラ井上
――展示されている作品の撮影に関する逸話や使用したライカのカメラおよびレンズについて、まだまだお聞きしたいことがありますのでどうぞよろしくお願いします。早速ですが作品を拝見したいと思います。

©高木誠
――これは単なる樹木を超えた実在感に満たされた写真です。この樹とはどのような出会いがあったのでしょう・
「これは上高地の奥にある化粧柳という河畔に生育する柳です。おそらく樹齢は200年を超えていると思いますが、この大樹が川のど真ん中に1本あります。ここは氾濫が多くて流木などもぶつかってくるのですが、化粧柳という木は根が深くて、それに耐えて生き続けているのです」
――枝の部分に盆栽で言うところの神(ジン)というか、枯れかかった部分もあるように見えます。
「僕が学生時代に見た時にはもっと若々しい姿だったんです。すごく大きくて元気のいい樹だったのですが、ここ10年でかなり弱ってきています」
――この場所を訪れるたびに、この樹と何十年も向き合い続けていらっしゃるんですね。
「だから『来たよ』とか『また今度来るからね』とか声をかけて帰ってくるわけです(笑)」
――ちょうどいい具合に山の端から光が差しています。
「季節は秋で、朝の光が逆光で入ってきた瞬間を、難しい条件でしたが撮りました」
アポ・ズミクロンで慣れ親しんだ老木の肖像を撮る
――機材はアポ・ズミクロンM f2/90mm ASPH.とライカM9の組み合わせとお聞きしました。
「マクロの90mmもあったけれどアポの方が接写以外は良かったのでよく使っていました。ライカM9はフレアやゴーストが見えないので、レンズの前に手をかざして斜めの光線がレンズに入らないようにして撮りました」
――手でハレーションを切りながら撮って、ライカM9はライブビュー未搭載ですから撮影した画像で確認しながら何枚も撮るという感じですね。

「ライブビューなら手持ちでもいけますが、この撮影では三脚に据えて撮っています。この光の条件ではフィルムではまずこのトーンは出ません。こういうコントラストの高い状況でもRAWで撮って調整すれば目で見た印象に近いものが出せます。この光ではコダクロームであれば撮っていません」
――フィルムであれば写真にできない光の条件で、何ロールもフィルムを使ったとしても作品にならないということですね。
「それがデジタルであればかなりシャドウも起こせますから見た目の印象に近づけられます。この写真もかなり調整しました」
――本当に、命というものを感じるいい写真だと思います。
ライカM11モノクロームの導き出す芳醇な質感

©高木誠
「これは上高地から少し入った明神池という場所です。季節は秋で、夜まで降っていた雨があがった朝なんです。もっと奥に泊まっていたのですが、雨上がりの明神池は多分霧が出て、谷も霧が出ると思って早起きして来て撮りました。谷から上がっている霧と明神池に陽が差して上がってくる霧の両方がバランスよく見えている瞬間を撮っています」
――これまたレンズはズマロン28mmですね。
「ズマロンとデジタルの組み合わせは緻密に写ります。これも絞りはF8ですが、撮った後に水と霧と光と森、それぞれの質感や奥行き、輝きや深みが出るように、全体を調整した後に個々にコントロールしてあります」
――湧き出してくるトーンのなだらかさも素晴らしいです。

「ライカM11モノクロームの力もかなりあります。カラーからモノクロ化してもこんな滑らかな階調は出ません。自然の持つ階調をそのまま再現する、すごいカメラですよ。ものすごく緻密ですから中判カメラを完全に超えています」
――となると、最近の機材はライカM11モノクローム1台だけですか?
「はい、それだけです」
――バックアップでもう1台ということはせず、潔く1台だけで山に入るのですね。
「もう1台欲しいですけれど、問題は体力です。もう1台持っていくとEVF込みで700g程度増えてしまうので」
――プラス700gの荷物によって自分の耐久力や集中力が削がれてしまうのであれば、それは置いて行った方がいいという判断ですね。いまのところ1台でもトラブルなく撮影は続けられているのですね。
「トラブルは1回もないですね。ライカのM系統は寒さにもびくともしません」
見渡す限り雲海に満たされた稀有な光景

©高木誠
「この写真はライカCLで撮っていますけれど、氷点下でもちゃんと動きますね。リチウム電池は寒さに強いです。昔は電池が寒さに弱かったので機械式一眼レフのライカR6.2ばかり使っていました。電磁シャッターの場合、電池の電圧が低下するとシャッターが切れなくなってしまうんです。今はリチウム電池になって耐寒性は良くなりましたね」
――レンズはエルマリートTL f2.8/18mm ASPH.とお聞きしました。
「小さい広角レンズで、感度400で絞りはf2.8の開放です。この時は、本当に素晴らしい状況でした」
――澄み切った空気感とキレの良さが際立っています。
「撮影したのは3月で、こんな雲海が出ることはまずありません。秋は雲海が出やすい条件の日がありますが、3月にこんな光景は見たことがないです。全くの無風で上空の気圧が雲を押さえているようで、見渡す限り雲海でした。山小屋から出た瞬間びっくりしました」
――ここまでパーフェクトな状況に出くわすチャンスはまずないのですね。
「一生に何回ですね。本当に海ですね。木曽の谷から飛騨高山まで全てが雲の下でした。この季節は寒くて風が吹いているものですが、これは神様がご褒美で見せてくれたと思うんです。僕の写真は全部山の神様が撮らせてくれたものですね(笑)」
親しみを込めた距離感で山の植物を撮る

©高木誠
「これはキヌガサソウという高山に咲く花です。白い花びら(正確には花びら状の花被片)と葉が同じく9枚で、もともと花というのは葉が進化したものなので基本的に同じ数になります。山の植物としては結構な大きさですね」
――カメラはライカM9、レンズはズミルックスM f1.4/50mm ASPH.ということなので被写体まで概ね1mくらいの距離感ですね。なだらかで美しいトーンが出ています。
「そうですね。非球面のズミルックス50mmはよく写ります。ライカM9は出てくる画像が柔らかいですから、撮った後にコントラストをつけて整えています」
――柔らかめの描写のライカM9と、解像力がありながら豊かなトーンを持つズミルックスM f1.4/50mm ASPH.という組み合わせの妙が出ている気がします。
ノクティルックス75mmの描写力と小さな命の気配

©高木誠
「これは大きな岩のあった涸沢カールで氷河地形の底のところです。新雪が来た朝に小さな足跡があって、これはヤマイタチ(オコジョ)だと思います。その軌跡が雪の曲面に美しく残っていたので撮ったものです」
――小さな命が、降りたての雪の上をつつつっっ!と進んでいった。これは山水画の世界ですね。
「動物の気配というものがこれでわかります。あと、影の形が面白かったですね。レンズはノクティルックスM f1.25/75mm ASPH.で雪の粒子の煌めきまで出ています。透明感がありながらそれでいて柔らかさもある、驚くべきレンズです。盛り上がっているところが膨らんで見えていますものね。これもレンズの性能でしょうね」
――なだらかな曲面の雪景色が反逆光でキラキラしています。しばらくしたらこの足跡も消えてなくなるわけですよね?
「雪が溶けたり風が吹いたりしたら無くなってしまうので、いい瞬間だったと思います。この辺りにずぅ〜っといると、いろんなものが見えてくるんです。それで見つかるわけです。ずぅ〜っといるとその場に体が馴染んできていろいろなものが見えるんですね」
――なるほど。あまりせかせかせずにじっくりと一箇所に留まるのが高木さんの流儀なのですね。
「このあたりが気に入ったとなると、2時間ぐらいはいます。だからよく『あなたまだここにいるんですか?』と登って降りて来た登山者に言われたりします(笑)」
――お話を伺っていると、普通の登山者であれば嫌なコンディションだなと思ってしまうような時に、むしろいい瞬間に出会えるのではないかと思っていらっしゃるように感じます。
「そうですね。晴れ続けて天候が安定し過ぎていると何ともならないですね。単調な光で雲も何もない時は非常に苦しいです」
――いわゆる、いい天気で山日和だと思われているような状況よりも、水や空気が動き続けている時こそ心が動くということですね?
「やはり自然の気配のようなものが感じ取れるし、深みが出る気がしますね。雨が降っている時もそうです」
――悪天候こそ受け入れるべき状況であり、そこに居るべきタイミングであると感じられるというのは正に修行ですね。
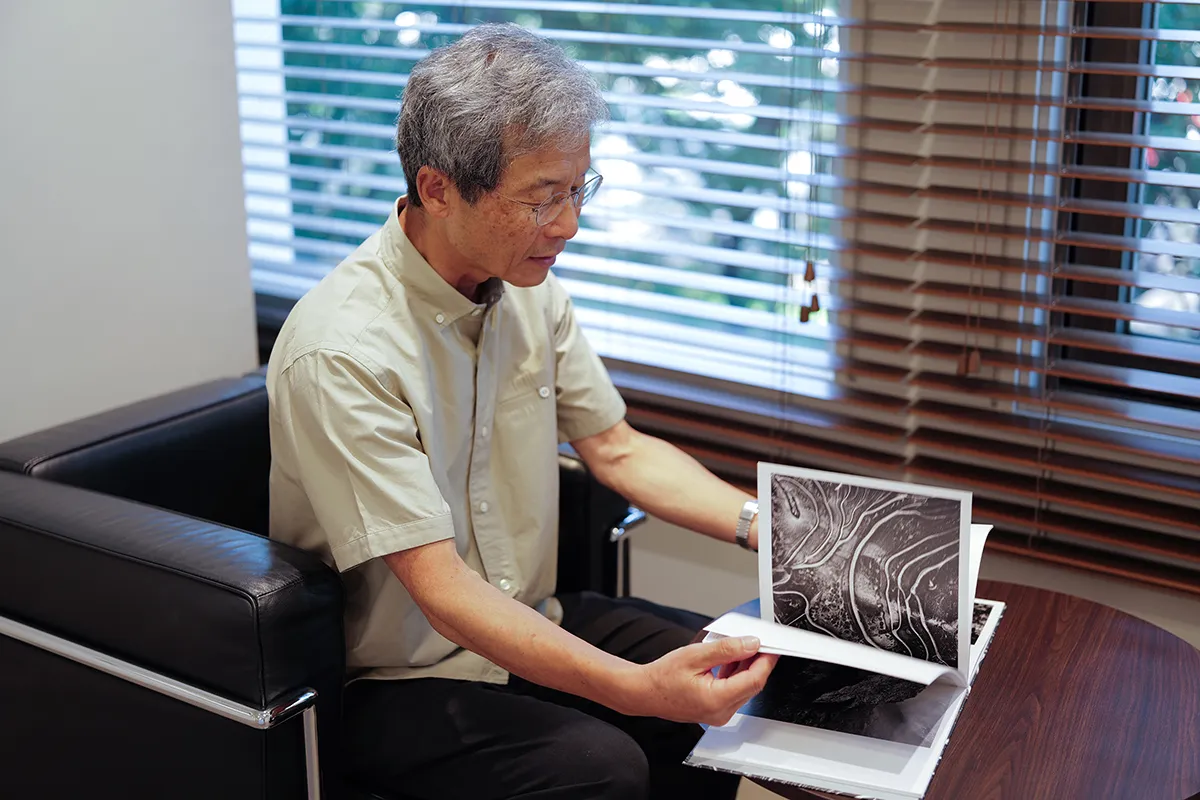
「しばらくここに居れば良いのではないかと分かってきます。それは同じ所、狭い範囲をものすごく歩いているので直観的に感じるんです。普通の人には見えないものが見えるし、感じられないものを感じられますね」
――何度も通うことでその場と共振していくような感覚が得られるのでしょうか?
「そうですね。自然科学の本や自分が感じていることと関係しているような書籍を常に読むものですから、実体験とそのような知識の組み合わせで人に見えないものが見えてくるんですね」
――ただその場に放り込まれるのではなく、なぜこのような自然環境が生まれているのか、自然の理(ことわり)みたいなものをよく理解した上で山に向かわれている。
「そうです。だからカメラを出す前に見て感じた時に、もうどんな写真になるかは決まっています。尊敬する山岳・自然写真家の水越武さんに考え方や取り組む姿勢などいろいろ指導していただいて、本当に多くを学びました。『見える時もあるし見えない時もある。でも、だんだん見えるようになってくる』『腰を落ち着けて取り組めば、必ず自然は応えてくれる』と。だから1テーマを10年はやってくださいと教わりました」
日本の自然のキーは、湿潤・多様性・移ろい

©高木誠
――この写真もある種のスピリチュアルな、生命の満ち満ちている波動を感じます。
「こちらは穂高の岩山とは違い、川を隔てて反対側に砂岩泥岩の安定した地層の山があり、そこには鬱蒼とした針葉樹の森が頂上付近まで発達しています。ロシアにあるタイガに近い針葉樹の森で、前日に雨が降った朝、山から降りてくる途中でこの光景に出会いました」
――地質学的なことが分かった上でこの場所の生態系の豊かさを感じていらっしゃることが写真に表出しているように感じます。
「それはありますね。上高地の山河ばかりを撮っているのは、そこの自然がものすごく多様だからです。岩の山、火山、森の山、そこから綺麗な川が流れていて河畔に瑞々しい森があり池もあり湿原もある。それだけ一箇所に揃っている場所はない。そこで撮れば日本人の自然観を表現できるだろう。だから上高地から動かないですし、動く必要を感じないのです(笑)」
――寂寞とした世界から数キロも動けばこれだけ潤沢な植生も見られるという、世界的に見てもここまでいろいろな要素が凝縮された場所は稀有なのだと気付かされました。
「日本の自然にとって最も大切なのは湿気で、それが多様な自然を育み、季節によりめまぐるしく移ろう。湿潤・多様性・移ろいが、日本の自然のキーだと思って撮影しています。だから、これからもここで撮ればいいなと考えています」
――機材はライカCLとズミルックスM 35mm/f1.4 ASPH
ということで、この場の植生の密度感が見事に捉えられていると感じます。
「35mmの非球面ズミルックスはライカM6との組み合わせで最初に買ったライカのレンズですが、いいレンズですね。ズミルックスの50mmよりは硬いけれど、奥行きが出るしライカCLでは画角が標準レンズになるのでちょうどいいんです」
マクロエルマーで幽玄の如く儚く美しい命を撮る

©高木誠
「これは、湿潤な森の暗闇に生きる、葉緑素を持っていないギンリョウソウという植物です。ユウレイタケとも呼ばれるように半透明で磨りガラスのような白さで少々不気味です」
――一体これは何なのだと、この写真を見ると震えます。
「モノクロだから余計にその感じが出ていると思います。レンズはマクロエルマーで撮ったのですが、よく写ったと思いますね」
――人知れず幽玄な命がここにあるのだと感じます。この写真、フルコースの料理で最後に今まで食べたことがないすごく美味しいデザートがでてきたような気持ちになりました。ちなみにサイズはあまり大きなものではないのでしょうか?
「10センチくらいですね。あまり大きくないのでマクロエルマーM90mmの出番です」
――カメラはライカM9とのことで、この組み合わせによって幽玄の世界観がよりうまく表現できている気もします。
「撮影はかなり前ですが、よく出ていると思います。やはり当時ライカM9は一番自然で立体感のある写真の撮れるカメラでした。値段は高かったですけどね(笑)」

――そして、決して扱いやすいカメラでもなかった記憶があります。だけどこのカメラでないと撮れないという、愛憎の混じり合った感情を引き起こすカメラでした。
「当時あの立体感を見たら、他のカメラはフラットで使えなくなるんですよね。そうなるともう買わざるを得なくて、それで買ったんです(笑)」
――いまだにあのコダックCCDはいいという人もいるほど個性的な描写でした。
「やはり普通とちょっと違いますかね。華やかさと渋さが共存したような色調でまろやかさもあってよかったですけれど、感度は上げられないなどの欠点もありました」
――とはいえ、これだけの作品が撮れるのであればいうことはないですね。
「そうですね。あの当時としては圧倒的に良くてデジタルの欠点というものが少なかった。ローパスフィルターなしにすることで緻密な柔らかさが出ていました」
これから使っていきたいライカとライカレンズについて
――これから使いたい機材について教えてください。
「カメラはライカM11モノクロームで満足していますので、メインの機材として使い続ける予定です。レンズに関してはコーティングされていない時代の古いものを今は使っています」
――もしかして戦前のタンバール90mm F2.2とか?
「そうです。タンバールを手に入れました」

――あのレンズは軟焦点のポートレートレンズという位置付けかと思いますが、どのような使い方をされていますか?
「開放近くで撮るとソフトフォーカスになりますけれど、絞っていくと非常にいい描写をするんですね」
――ソフトフォーカス用の真ん中の光線を遮るフィルターは付けたままでしょうか?
「フィルターは装着しません。F12.5辺りになると完全に球面収差、ソフトフォーカスの効果がなくなってくるのですが、その時の描写の立体感と柔らかさには驚きました。F5.6辺りになるとちょっと球面収差が出てきて、そこもうまく使えばタンバールということが分からずに撮れると思います」
――なるほど。さりげなく、たとえばハイライト部分に微妙な滲みが出ているような感じとか。
「そういうのはありますね。あとはズミクロンの5cmの最初期のものです」
――というと沈胴でスクリューマウントの時代ですね。

「ガラスにトリウムが含まれている時代のもの、あれはいいですね。固定鏡筒になると形やエッジをカチッと描写するのですが、トリウムズミクロンはそのものがそこにあるかのような立体感が出ますね。それでライカM11モノクロームで撮ると、そこに本当にあるのではないかという感じです。スチールリムのズミルックス35mm F1.4もいいですけれど、ズミクロンの方がより自然ですね」
――50mmであれば画角もパースペクティブも自然ですしね。
「あのレンズはいいですよ、トリウムを使わずにあの描写を復刻してもらいたいぐらいです。タンバールは復刻されましたが、ライカはデジタルの欠点をよく理解していると思います。立体感や空気感を出そうと思うと昔のレンズの要素を入れ込んだ方が効果的です。古い設計のレンズはスペックとしては悪いかもしれないけれど、実際に撮った写真の実在感・存在感はいいものが出るとライカも思っているのではないでしょうか」

――ゆくゆくはタンバールや初期の沈胴ズミクロンで撮られた作品を拝見させていただけると思うと楽しみです。
「ノクティルックスの復刻版もいいですね。繊細でちょっとシャープだけれど、あれもよく考えられたいいレンズです。開放付近では立体感のあるボケが出ますし、絞ってF11くらいにしていくと回折で少し柔らかくなるんですね。変な使い方ですけれどその辺りの絞りにすることで中判や大型カメラで撮ったような画質が得られます」
――レンズの回折現象の折り返し地点を探りながら、上高地の光景を撮影しているのは高木さんただ一人だと思います(笑)。
「ライカM11モノクロームで撮ると、その折り返し地点がよくわかりますよ。だからレンズをテストしているようなカメラですよ。EVFで見ただけである程度分かります」

――それは、コダクロームで撮影されていた時代ではできない写真術とも言えそうです。
「できないですね。デジタルだからできることはいっぱいありますよ」
――フィルム時代の写真の常識では無理だけれど、自分の目と脳で感じていることを表現したい時にデジタルであれば再現できるということですね。
「再現できます。ただし再現するには撮る技術が50%、その後の現像処理・プリントの技術が50%です。だから最初の50%だけしか使っていないとうまく表現できません」
――ポジフィルムの時代では、撮った時点で決着がついている感じでしたが、その後のプロセスも必須ということですね。
「自分の感じたもの、見たものを最後に調整して作っていくということになります。あとはM型ライカを使っていて言えるのは、シンプルで余分なものがついていないから撮れるんです。ボタンの多いカメラは私の撮影には合わないんですよ」
――カメラの表面に物理スイッチを沢山並べたカメラは、同時に数多くの判断を強いてくる感じがします。さまざまな選択肢が目に入ってくるので迷いが生じてしまいます。

「挙句変なところを押してしまって動かなくなるという(笑)。レンズは事前にテストして描写特性を把握し、主に使う絞りにマークしてあるのでそこに合わせるだけでよく、それに応じてヒストグラムでシャッター速度も決まり、手振れが心配なら感度を上げればいい。ピントはEVFで高精度に合わせられます。シンプルだから、撮っている時にカメラは存在しないんですね。被写体と自分だけで、カメラはありません。最終的にあるのは自然だけで、自分というものもなくなります」
――自然と一体化して、高木誠という一個人のエゴが消失する瞬間にシャッターを切るということですね!その状態になることの妨げにならないカメラというのは、なかなかないですよね。
「あのカメラしかないです。だからライカM型、今はM11モノクロームを使っていますが、これ以外のカメラを使う気が起きません。ライカM型はフィルム時代はルポルタージュに最適なカメラでした。それがデジタル化に伴い、中判を超える高精細画質、高感度対応、さらにEVFで光や構図を実絞りで正確に把握できるようになり、元来のシンプルなボディと極めて小型・軽量な高性能レンズ群と相まって、持ち歩いてじっくり撮る風景写真などにも最適なカメラへと生まれ変わったと、私は実感しています」
――今後もライカを生涯の道具として使い続けていこうという感じですね。
「もちろんそうです。今は他に比較できるものがないですから。ライカは昔以上の品質でボディも作っているし、本質を見抜いてぶれずによくやられていると思いますよ。逆に言えば他のメーカーのカメラと違うから皆さんが欲しがっているのではないでしょうかね」
――高木さんの論理的かつスピリチュアルな世界認識を写真で表現するにはライカとライカレンズが必要であるということがよく分かりました。日本人の自然観への高木さんの洞察と、それに基づいた撮影エピソードも極めてエキサイティングでした。本日は長時間の取材にご対応いただき、どうもありがとうございました。
「こちらこそ、どうもありがとうございました」
写真展概要
| タイトル: | 生きている大地 |
| 期間 : | 2025年7月1日(火)- 2025年11月6日(木) |
| 会場 : |
ライカ松坂屋名古屋店 愛知県名古屋市中区栄3-16-1松坂屋名古屋店 北館3階 Tel.050-5785-4466 |
| 営業時間: | 10:00-20:00 |
高木誠 / Makoto Takagi プロフィール
1957年愛知県岡崎市生まれ。
1984~1994年二科展入選7回。2000年写真展「自然を撮る―5人の目」を水越武写真展「今、地球を歩く」と同時開催(豊田市美術館)。2001年「生きている山」で第1回田淵行男賞受賞。同年に写真展「山学独歩」(安曇野山光ホール)。2010年写真集『氷河の消えた山』(東京新聞)出版。2019年写真展「時の呪力」(田淵行男記念館)。2024年写真集『生きている大地』(ふげん社)出版、同時に写真展開催。