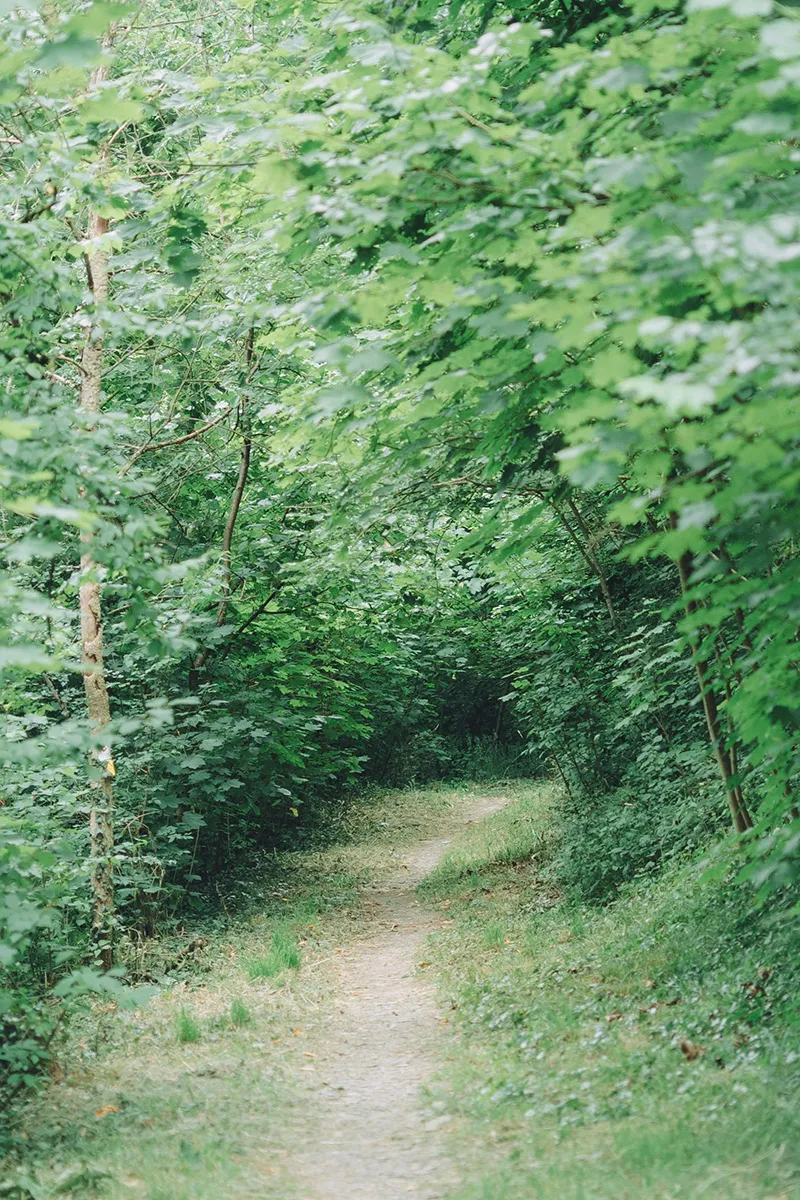100 YEARS OF LEICA
ライカカメラを生んだ街・ウェッツラーへの旅 後編
「ウェッツラーの街角で」
石井朋彦
ライカを生んだ土地・ウェッツラー
ゲーテの生まれたフランクフルトから、自動車でアウトバーンを走り、50分あまり。
ライカカメラ社創業の地・ウェッツラーで、「ライカI型」誕生から100年を記念する式典「100 YEARS OF LEICA」に参加するという光栄な機会に恵まれました。
ゲーテが、愛した女性・シャルロッテとのウェッツラーにおける記憶を元に書いた名作「若きウェルテルの悩み」を車中で読み返しながら、予感めいた想いが胸中に膨らんでゆきました。
ゲーテがシャルロッテと共に見たウェッツラーの自然の中で、ライカのカメラとレンズが彼の地で生まれた理由を見いだせるのではないか ── と。
ウェッツラーを訪れることは、ライカのカメラを愛する者として格別な体験です。ライカの技術者、オスカー・バルナックが開発した世界初の35mmフォーマットのカメラ「ライカI型」が発売されて、今年で100年。写真史に多大な影響を与えたライカのカメラ100年の歴史を祝う式典は、旧市街の中心にそびえる大聖堂でのコンサートに始まり、本社が置かれている「ライツパーク」における様々なイベントや100周年を記念する製品の発表、オークション ── と、壮麗なものでした。
ライカカメラ社社主、アンドレアス・カウフマン氏とカリン・カウフマン氏のスピーチが、今も耳に残っています。
「我々の使命は、ウェッツラーから世界へ、写真文化と写真家を送り出すことである」
カメラメーカーでありながら、企業理念の骨子には、カメラを手に写真を撮る写真家と、その作品がある。
ライツパークの中には、数々の歴史的瞬間を記録した写真が展示され、式典には生ける伝説と呼ぶべき写真家たちが、参加していました。
式典に登壇した、アメリカを代表する写真家、ジョエル・マイロウィッツ氏はこう語ります。
「M型ライカで光学ファインダーと、もうひとつの『目』で現実を見据えながら撮るという行為は、世界との調和である」
ウェッツラーの旧市街へ
ウェッツラーの中心部から東へ1kmくらいの高台に広がるライツパークから、市街へ歩いて30分ほど。ラーン川の周辺に広がる、ウェッツラーの旧市街を訪れる旅人は多くないそうです。「100 YEARS OF LEICA」の余韻に浸りながら、ウェッツラーの街を、カメラを手に歩きました。
ドイツ連邦共和国ヘッセン州ギーセン行政管区ラーン=ディル郡の市であるウェッツラーは、東西に流れるラーン川の南側に広がる、人口55000人ほどの小さな街です。新市街と旧市街を分かつ橋のたもとで、プレッツェル(塩気の強いねじりパン)を齧りながらコーヒーで唇を湿らせて一息つき、ライカカメラ社の歴史を振り返ります。
1849年、ドイツの光学技術者、カール・ケルナーがウェッツラーに顕微鏡メーカー「オプティシェス・インスティトゥート(Optisches Institut )」を設立します。ケルナーの死後、妻が会社を引き継ぎ、再婚した社員ベルトレが継承。「ケルナー&ベルトレ」と社名を変えました。
1865年、ケルナーは、スイスの時計メーカーで働いていた若き機械工、エルンスト・ライツ一世を雇い入れます。1869年にベルトレが亡くなると、ライツ一世が経営を引き継ぎ、自らの名を冠した光学メーカーへと成長させてゆきました。
1911年、ライカのカメラの生みの親、オスカー・バルナックがエルンスト・ライツ社に入社します。バルナックは映画用カメラを試作する過程で、小型のスチルカメラの着想を得ます。当時は大型カメラが主流でしたが、病弱で小柄だったバルナックは、自らも扱える軽量カメラの試作を試みます。
1913年、35mm映画フィルム2コマ分を使った試作機「ウル・ライカ」を完成。1920年にライツ一世が亡くなると、後を継いだライツ二世がウル・ライカの可能性に注目し、周囲の反対の声を押し切って小型スチルカメラの製造を決意。1925年、オスカー・バルナックはコンパクトで扱いやすい初の市販機「ライカI」を発売。この小さなカメラが、写真の歴史を塗り替えることになります。
スマートフォンやコンパクトカメラが普及するはるか昔、オスカー・バルナックが片手に収まる小型カメラを開発したことによって、写真家達がカメラを手に世界を旅し、歴史的瞬間を記録し続けてきた。すべての人々が写真を撮るようになった現代の写真文化は、このウェッツラーの街から始まったのです。
100年前と同じく、滔々と流れを続けるラーン川沿いを歩きながら、なぜライカのカメラが、ウェッツラーという自然豊かな土地で生まれたのかに想いを巡らせ、「ライカ M10-P」 と「 アポ・ズミクロンM f2/50mm ASPH. 」を手に、シャッターを切り始めました。
若きウェルテルの悩みの舞台となったウェッツラー
ラーン川にかかる橋からウェッツラーの旧市街を望みます。
街は、高台にそびえるウェッツラー大聖堂へむかって、無数の路地と坂を登ってゆく地形になっています。豊かな水をたたえたラーン川沿いには、カフェやビアガーデンが広がり、住人や観光客がビールやワインを片手に談笑していました。
神聖ローマ帝国の最高裁判所が置かれていたウェッツラーは、前編で記した通り、ゲーテが「若きウェルテルの悩み」のヒロイン、シャルロッテのモデルとなった女性と出会った土地です。モデルとなった女性の名は、シャルロッテ・ゾフィー・ヘンリエッテ・ブッフ。1753年にウェッツラーで生まれ、1828年にドイツ北部ニーダ-ザクセン州の州都・ハノーファーで生涯を閉じました。
1772年初夏、ウェッツラー近郊の舞踏会で、ゲーテはシャルロッテと出会います。シャルロッテの聡明さと素朴さと美しさにゲーテは一目惚れし、彼女の家を何度も訪ねては、詩や手紙を送ったそうです。
しかし、シャルロッテには、ゲーテの友人だったケストナーという許嫁がいました。三人は固い友情で結ばれ、ケストナーはゲーテのシャルロッテに対する想いを知りながらも、友人関係を続けたそうです。
叶わぬ想いに胸を引き裂かれたゲーテは、ウェッツラーを去りました。
ゲーテの手記によると、ゲーテとシャルロッテは、ウェッツラー郊外の自然の中を歩き、心を通わせたそうです。シャルロッテの家は旧市街にあったとされていますので、ふたりは何度も、この橋の上を歩いたことでしょう。
オスカー・バルナックがはじめてシャッターを押した場所で
橋を越えた先に広がるドーム広場から少し歩いた先にあるアイゼンマルクト(Eisenmarkt)広場には、オスカー・バルナックが試作機「ウル・ライカ」で撮影を行なったY字路があります。
先日、M型ライカ誕生から70周年を記念して発売された「ライカM Edition 70」を手に入れました。記念すべきカメラで撮影する一枚目は、この場所で撮ると決めていました。ネガフィルムを装填し、オスカー・バルナックがカメラを構えたとされる場所で跪き、シャッターを切ります。
どこか、遠いところでシャッター音が響いたような気がしました。
帰国した今も、あの瞬間の空気や光が脳内に蘇ります。私は現代のウェッツラーにいたのか。それとも、100年以上前、オスカー・バルナックが息をひそめながら「ウル・ライカ」のシャッターを切った瞬間にいたのか……。
前編で記した、ゲーテの「色彩論」に想いを馳せました。光を数学的に照明したニュートンの光学理論を否定し、黒と白、光と闇の間から色が生まれると考えたゲーテは、色彩は見る者の目によって存在すると唱えました。
スマートフォンやミラーレスカメラが普及し、液晶画面やEVFで、撮影結果をリアルタイムに確認しながら撮影できるようになった現代。100年前から変わらないレンジファインダー(距離計)機構を備えたM型ライカは、ガラスで素通しの光学ファインダー越しに被写体を捉えます。光学ファインダーと、その場で見た被写体や風景の色彩や空気感、匂いや感情を記憶に刻むこと。これこそ、100年続くライカのカメラを手にする醍醐味なのではないでしょうか。
ウェッツラー大聖堂へ
オスカー・バルナックと、100年、数多くのカメラとレンズをこの地で生み出してきたライカの技術者に敬意を表しながら、大聖堂へと歩きます。ウェッツラーの街は、半日もあれば回れてしまうほどこじんまりとした街ですが、路地が多く、三日間の滞在中、何度も路地裏に迷い込み、中世ヨーロッパにタイムスリップしたような感覚に襲われました。
息を切らせて坂道を登ると、オープンテラスのカフェが並ぶ少し開けた道の先に、ウェッツラー大聖堂が見えてきます。片方の塔が未完で、ゴシック様式とロマネスク様式が混合したとても珍しい教会だとか。丸いアーチ型のロマネスク建築様式と、鋭角で硬質なゴシック建築の融合する様は、ライカのカメラのデザインや設計思想を想起させます。宗教改革後は、現在もカトリックとプロテスタントの両宗派の信者が訪れているそうです。
「なぜ、ライカのカメラとレンズは違うのか」
そう問われることがよくあります。
写真家によって、その答えは様々です。ライカの達人であり、スナップ・ポートレートの名手、ハービー・山口さんは「被写体の心までも写せるだろう」と表現しています。現代のレンズは、かつて職人がガラスを手で磨いていた時代から、現代はナノレベルまで、人間の手の及ばない精度で磨き上げられ、MTF(Modulation Transfer Function=変調伝達関数)を極限まで高めるようになりました。多画素センサーと、コンピュテーショナルフォトグラフィー、生成AIの登場によって、画像や映像の精度は日増しに高まっています。
オートフォーカス機構も、最新のグラフィックエンジンも搭載していないライカのカメラが何故現代においても写真家を魅了し続けるのか。
オスカー・バルナックが発想した、手のひらに収まるサイズのカメラであること。
レンジファインダー(距離計)カメラという機構が、被写体との距離感を測りながら撮影することにむいていること。
しかし、それだけではないと考えるのです。
この旅で、ライカのカメラとレンズが描き出す光と影、色彩の本質に、近づけたような気がしています。
ゲーテが恋する女性との語らいの中で見出した、ウェッツラーの自然。ニュートン的光学論よりも、ゲーテ的色彩論が生まれたこの地だからこそ、数学的・光学的な品質を越えた、心象風景までを写し出すライカのカメラとレンズが生まれたのではないか。
光と影、そして見る者の心の中にこそ、色彩は存在する。
ゲーテが愛するシャルロッテと見た風景と、オスカー・バルナックと彼の意志を受け継ぎ、今も製品を作り続けている技術者の見ている世界と、ライカのカメラとレンズの品質は不可分ではないと考えるのです。
最新のデジタルカメラが最新機能とスペックを競い合う中、100年もその根本的な構造が変わらないライカのカメラは、あくまでも私見ではありますが、ニュートンの光学的カメラではなく、文学・芸術に根ざした、ゲーテ的なカメラと言えるのではないでしょうか。
ゲーテがこの世を去る前に「もっと光を」という言葉を遺したというエピソードは有名です。
死を前にし、失われてゆく視界の中で「窓を開けてくれ」と言ったにすぎない……という説もありますが、ライカのカメラを手にウェッツラーを歩きながら、想像します。
ゲーテは、愛したシャルロッテと共に記憶の中に刻んだウェッツラーの自然が織りなす光と影、色彩を見ていたのではないか──と。
ゲーテの「色彩」を生んだウェッツラーで生まれたライカのカメラとレンズを手に、これからも眼の前を流れてゆく風景を撮り続けたい……と、暮れなずむウェッツラーの街を見下ろしながら考えました。
使用機材
Leica M10-P・Leica APO-SummicronM f2/50mm ASPH.・Leica M Edition 70
石井朋彦 / 写真家・映画プロデューサー
「千と千尋の神隠し」「君たちはどう生きるか」「スカイ・クロラ The Sky Crawlers」等、多数の映画作品に関わる。
写真家としても活動し、ライカGINZA SIX、ライカそごう横浜店、ライカ松坂屋名古屋店、新宿 北村写真機店で写真展を開催。
雑誌「SWITCH」「Cameraholics」等に、写真・寄稿多数。JR高輪ゲートウェイ駅前の仮囲いデザインの撮影・ディレクションを行った。
M型ライカを手に、写真撮影における「距離感」をテーマに、写真の魅力を発信し続けている。